こんにちは、秋富です。
このブログでは、農業法人等に雇用されて農業をする、「サラリーマン就農」を推奨しています。

サラリーマン就農に興味はあるけど、農業の知識や経験もないし、転職してからうまくやっていけるかなぁ
このような不安をお持ちの方は多いと思います。
私もほぼ未経験で農業法人に就職しましたが、転職活動中も採用が決まってからも、不安でいっぱいでした。
この記事では、未経験から農業法人に転職する時に抱えがちな不安とその解消方法について、私の経験もふまえて解説します。
未経験者が抱えがちな6つの不安とその解消方法

それでは、未経験者が抱えがちな不安とその解消方法を見ていきましょう。
| 不安の種類 | 解消方法 |
|---|---|
| 農業の知識や経験の不足 | ①農業に関する入門書を読む ②家庭菜園をやってみる ③転職先のフォロー体制を調べる ④関係する資格の勉強をする |
| 収入が下がる | ①お金について学びなおす ②給与体系を確認する ③副業を検討する |
| 身体的な負担が大きい | ①身体を動かしてみる ②農業を体験してみる |
| ワークライフバランスが崩れる | ①勤務時間や繁閑差をしっかり確認する ②休息の質を高める |
| 機械の運転に自信がない | ①就職後のフォロー体制を確認する ②資格や免許を取得する |
| キャリアプランが描けない | ①自分のキャリアについて考える ②面接などで確認する |
不安1:農業の知識や経験の不足
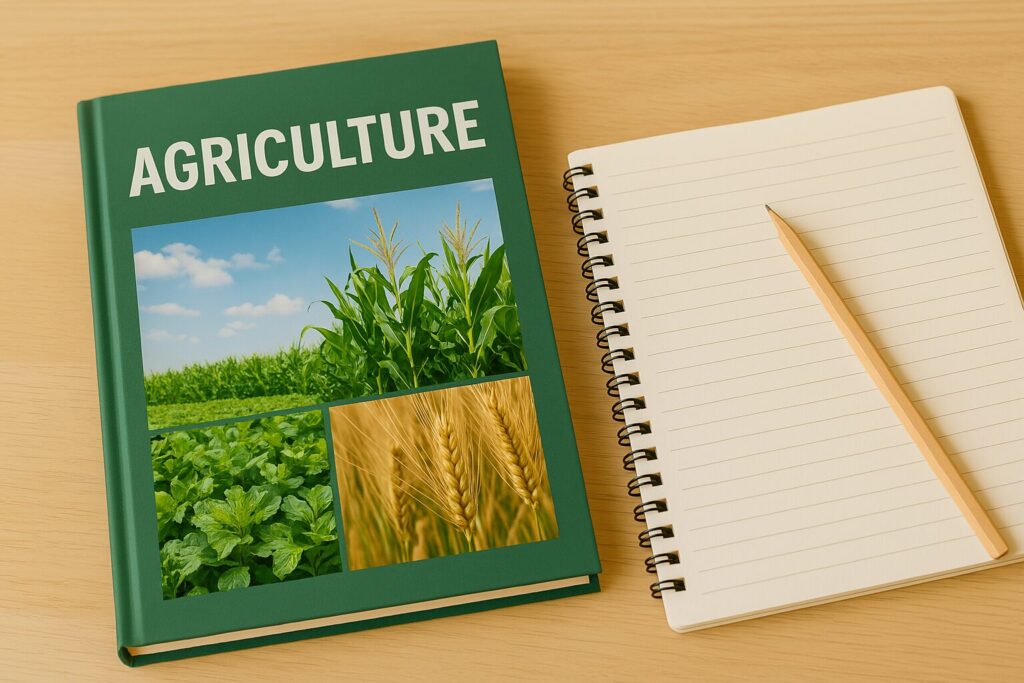
農業に関する知識や経験が少ないと、転職後うまくやっていけるのか不安になります。
特に農業は、経験豊富な農家が独自のすごい技術を持っているようなイメージがあり、未経験者がうまくやっていけるのか、気になる人も多いと思います。
解消法1:農業に関する入門書を読む
まずは農業について知ることが不安の解消につながります。
書籍などで農業の基礎知識を身につけましょう。
最初はあまり専門的なものではなく、初心者向けの入門書から読むのがおススメです。
『最新 日本の農業図鑑』
一番最初に読むならこの本だと思います。
日本農業の実情や歴史、肥料や農薬、各農作物(稲作、畑作、果樹など)や畜産に関する基礎知識まで幅広く書かれています。
さらに、スマート農業やバイオテクノロジー、SDGsなど最近の動向にも触れられており、農業に関する総合的な知識を身につけることができます。
文章も平易で分かりやすく、専門的な用語は欄外で説明してくれています。
『図解でよくわかる 農業のきほん』
野菜・果樹・畜産などの基礎知識やスマート農業などの新技術、農作物の流通といった幅広い内容が書かれています。
本書の大きな特徴は、植物の構造や光合成の仕組み、土壌の基礎知識や施肥など、作物の栽培に関する説明が豊富な点です。
栽培管理の基礎知識、野菜・果樹など作物ごとの栽培管理のポイントなどについてまとまった知識を得ることができます。
『図解即戦力 農業のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』
スマート農業など、農業の新しい技術について詳しく説明されているのが本書の特徴です。
また、農業や関連する業界(例えば卸売業、種苗メーカー等)の動向や今後の展望も書かれており、新しい農業の動きを把握するのにおススメの一冊です。
こちらの本については当ブログの別記事で詳しく紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
解消法2:家庭菜園をやってみる
農業に関する経験を増やすために、実際に野菜などを栽培してみるのもおススメです。
自宅で育てる家庭菜園のほか、市民農園など畑を借りて栽培する方法もあります。
私も東京で家庭菜園と市民農園、それぞれで野菜を育てた経験があります。
土づくりや苗の植え付け、雑草取りなど実際の農作業を通して農業の大変さが身をもって分かりました。
特に市民農園では、週末しか作業できないこともあり、畑の雑草取りがかなりきつかったです(除草だけで一時間以上かかる時もありました)。
そして苦労した分だけ、育った野菜を収穫する時の喜びはとても大きかったです!
今の仕事でも、この時の経験を活かせています。
例えば、雑草を発生させないように事前に打つ手を決める、農作業スタッフの負担を軽減するために工夫する等、様々な場面で役立っています。
初めての人には、トマトやナスがおススメです。
プランター1つからでも育てることができますし、手間もそれほどかかりません。
近所に市民農園がある人は、そこで作物を育ててみるのもおススメです。
申請方法、使用料やルールなどは各自治体によって異なります。
興味のある方は「お住まいの市町村名+市民農園」で検索してみましょう。
また、最近では民間企業が運営する貸し農園もあります。
もっとも有名なのは「シェア畑」でしょう。
東京や千葉、愛知、大阪などを中心に規模を広げているようです。
民間の貸し農園は、市民農園に比べて利用料が高いですが、道具の無料レンタルやアドバイザーによる講習会など、手厚いサポートが売りのようです。
解消法3:転職先のフォロー体制を調べる
求人サイトやハローワークの求人情報を確認する際、その会社の研修制度や先輩社員からのフォロー体制の有無を調べることも重要です。
記載がない会社に対しては、こちらから積極的に質問して確認しましょう。
求人情報に「経験不問」や「未経験者歓迎」などと書かれている企業の場合、経験のない人が応募してくることは想定済みなので、遠慮する必要はありません。
質問時に大切なのは、「一生懸命頑張りたいし、積極的にチャレンジしたいけど、未経験の部分が不安です」と、まずやる気をしっかり伝えることです。
私も3社くらいの農業法人と面接をしましたが、未経験者への教育体制やフォロー体制は必ず確認しました。特に嫌な顔をされることはなく、むしろ「やっぱり気になるよね」という反応が多かったと記憶しています。
面接時以外でも、転職エージェントを活用すれば、代わりに企業に確認してもらうこともできます。
農業専門サイトの転職エージェントの活用については、以下の記事で紹介していますので、チェックしてみてください。
解消法4:関係する資格の勉強をする
農業を始めるにあたって、必須となる資格は特に必要ありません。
しかし資格の勉強を通じて農業に必要な知識を習得できます。
時間とお金に余裕のある人は、資格の取得を目指してみるのも良いでしょう。
おススメの資格は以下の通りです。
日本農業検定
「栽培」「農業全般」「環境」「食」に関する基礎知識の習得を目標とした資格制度です。
農業や栽培だけでなく、食に関する基本的な知識も身につけることができます。

農業技術検定
公式ホームページで以下のように説明されています。
日本農業技術検定は、わが国の農業現場への新規就農のほか、農業法人・関連企業等への就業をめざす学生や社会人などを対象に、農業界の人材育成・確保にむけて、農業の知識や技術の修得水準を客観的に把握し、教育研修の効果を高めることを目的とした全国統一の農業専門の試験制度です。
日本農業技術検定試験のご案内
このように、日本農業検定よりも専門性が高い試験となっています。
日本農業検定の勉強をしてみて、「簡単すぎる」「より専門的な知識を得たい」と思った人は、挑戦してみるのもおススメです。

土壌医検定
ほとんどの農業で重要になる「土づくり」について、その専門家となる人材を育成するための資格試験です。
1級から3級まであり、1級に合格した人は「土壌医」の資格名を名乗ることができます。
土壌関係は私自身も勉強中です。内容が専門的でなかなか取っつきにくいんですよね。
資格取得を目指すというよりは、資格の勉強を通して土壌について学ぶという目的で始めると良いと思います。
興味がある方は、まず3級のテキストや過去問を見てみてはいかがでしょうか。
不安2:収入が下がる

農業法人の求人票などを眺めていると、給与が少なく感じる人もいると思います(私もそうでした)。だいたい月収20~25万円のところが多い印象です。
また、ボーナスの支給額については、求人票に記載がないところがほとんどです。
私が働いている農業法人では、その年の売上や収益等を考慮してボーナスの有無を決め、さらに貢献度や勤続年数に応じて社員ごとの支給額を決めているようです。
前職でボーナスもしっかりもらっていた場合、転職によって大きく年収が下がってしまうことに不安を覚えてしまうと思います。
解消法1:お金について学びなおす
まずはお金についてしっかり学んでみましょう。
お金に関する考え方については、両学長という人のYouTubeがとても参考になります。
かなりたくさんの動画を出されていますが、初めての人は以下の「お金の勉強 -初級編-」から見始めるのが良いと思います。
また、最近は本も出版しているようです。
解消法2:給与体系を確認する
応募先企業の給与体系を確認することも重要です。
初任給は求人票で確認できますが、昇給や賞与などについては面接等で確認してみましょう。
昇給については、勤続年数に応じて上がっていくのか、役職に就くことで昇給するのか、業績に応じて一律で上昇するのか等、企業によって仕組みが異なります。
賞与も同様で、必ず出る企業もあれば、その年の業績によって賞与の有無が決まる場合もあります。
また、昇給や賞与に関する決まりがない企業も存在します。
その場合、どんな人が(例えば、年齢や役職など)、どれくらいの給与をもらっているのか、答えられる範囲で教えてもらうようにしましょう。
聞きにくい質問ですが、入社後にミスマッチが起こるのはお互いにとって不幸でしかありませんので、ためらわずに確認してみることをおススメします。
解消法3:副業を検討する
企業にもよりますが、農閑期は就業時間が短くなったり、長期休暇が取れるような農業法人も存在します。
私が働いている農業法人の場合、農閑期である冬期には15時で定時となり、年末年始の休暇は3週間もあります。
このような時間や休暇を利用して、副業を始めてみる方法もあります。
私の場合、このブログも基本的に平日夕方の時間を中心に執筆しています。
また、クラウドワークスというサイトを使って細々とライティングの仕事も受注しています。
副業で時間や体力を使い切って本業に支障をきたすのは本末転倒ですが、無理のない範囲で自分にできる副業にチャレンジしてはいかがでしょうか。
本業と異なる仕事をするという経験は、自身のキャリアにとっても重要です。
副業の見つけ方としては、クラウドワークスやランサーズなど、フリーランス向けの案件紹介サイトがあります。そこに登録してみて、自分に合いそうな案件を探してみましょう。
閲覧だけならば未登録でも可能ですので、一度どんな案件があるのか見てみるのが良いと思います。
また、私は経験がありませんが、タイミーなどを使って、スキマ時間を活用した単発のアルバイトをするのもアリです。
不安3:身体的な負担が大きい

一般的に、農業=肉体労働のイメージが強いと思います。
特にこれまで運動習慣がない人はやっていけるのか不安に思うかもしれません。
最近では、高齢化や後継者不足の影響を受け、農作業の省力化・効率化が急ピッチで進んでいます。
しかし、未だ人の手による作業も多く、体力を必要とする場面が少なくないのも事実です。
私が働いている農業法人の場合、機械でダイコンを引き抜いていくのですが、そのダイコンを鉄製のコンテナに入れるのは手作業になります。
約1m四方のコンテナが満杯になるまで休みなく、一度に3~4本のダイコンを抱えて入れていく作業はかなり重労働です。
解消法1:身体を動かしてみる
これまで運動する機会がなかった人は、これを機に身体を動かす習慣をつけてみましょう。
電車で通勤している人なら、歩く距離を増やす、家で筋トレしてみる等、できることから始めてみてください。
私の場合、自宅の最寄りの一つ前の駅で降りて歩くようにしたほか、昼休みも20分くらい散歩するようにしました。
大事なのは、いきなり強い負荷をかけすぎないこと。
気合を入れてやるのは良いのですが、きつ過ぎるとなかなか長続きしません。
一日15分歩くだけでも、それが習慣化できればどんどん歩く時間は増えていきます。
最初はすごくゆるいレベルから始めてみましょう。
お風呂上がりのストレッチで身体をほぐすだけでも良いですよ。
YouTubeに様々なストレッチ動画があるので探してみてください。
私のおススメは「オガトレ」というチャンネルの動画です。
初心者や身体の硬い人でも始めやすい動画がたくさんあります。
解消法2:農業を体験してみる
実際に農業を体験してみて、どれくらい身体に負担がかかるものなのか、イメージを掴むのも一つの方法です。
先に紹介した市民農園で野菜などを作ってみるのも良いでしょう。
また、近所で農業体験などが行われていれば、そちらに参加してみるのもアリです。
農家個人が実施している場合や、行政や農協が農業体験の受け入れを行っていることもあります。
興味のある方は「お住まいの市町村名+農業体験」で検索して調べてみましょう。
一例として、東京都日野市の場合、市のホームページで農業体験のできる農家が紹介されています。

また、援農ボランティアと言って、人手が足りない農家の手伝いをするシステムもあります。
ボランティアという形で農業を体験することができますので、こちらも興味のある方は調べてみてください。
ちなみに東京都の場合、農家と援農ボランティアのマッチングサイトを行政が運営しているようです。
不安4:ワークライフバランスが崩れる


農業は毎日作業があって、休みなんてあってないようなものじゃないの?
こんな印象を持っている人もいるでしょう。
農業法人では、就業時間が定められていたり、決まった休日が設定されていることがほとんどです。
ただし、農業は季節によって繁閑差があることが多いため、作業が集中して忙しくなる時期が出てくることもあります。
また、雨で作業が遅れた場合など、どこかで埋め合わせのために長時間働かざるを得ないことも……。
このように勤務時間や休日が変動しやすい働き方に慣れていない人は、農業法人で働くことに躊躇うこともあると思います。
解消法1:勤務時間や繁閑差をしっかり確認する
何よりもまず希望する企業の勤務時間や季節による繁閑差を確認することが大切です。
求人情報や面接などで確認しましょう。
企業によっては繁忙期と農閑期それぞれの勤務時間を書いてくれているところもありますが、はっきり記載がない場合もあります。
面接前にそれらの情報を知りたい時は、転職エージェントなどを通して企業に確認してもらうのも一つの手です。
私が転職活動をしていた時は、以下の項目を確認するようにしていました。
- 季節によって勤務時間は変わるのか。変わる場合、最も忙しい時期の勤務時間はどれくらいになるのか。
- 繁忙期の休日はどのように設定されているのか。
- 繁忙期に年休は取得できるのか。
- 休憩時間の有無とタイミング
繁忙期の勤務が早朝から始まるような企業では、平日の余暇時間がなかなか取れないこともあります。
繁忙期の勤務時間に合わせて、仕事以外の時間の使い方を考えることも重要になってきます。
解消法2:休息の質を高める
こちらは入社してからの解消法になりますが、参考までに説明します。
特に繁閑差のある企業では、繁忙期は休みが少なくなったり、勤務時間も長くなることが一般的です。
農業では肉体労働も少なくないため、疲労がたまると作業中の事故にもつながりかねません。
休むときはしっかりと休むことが重要になってきます。
睡眠時間をたくさん確保できれば良いのですが、それができない場合は、睡眠の質を高めることが重要です。
睡眠の質を高めるために私が意識しているのは次の2つです。
- 寝る3時間くらい前から部屋の明かりを暗めにする。
- 寝る前にスマホは見ないようにする。
自分に合った方法で、睡眠の質向上に取り組みましょう。
不安5:機械の運転に自信がない

農業に従事する人にとって、トラクターなど農業機械の運転は避けては通れないでしょう。
(品目によっては必要ない場合もありますが……)
また、基本的には出勤や畑への移動には車がメインになるため、車の運転も必須だと考えましょう。
現場によっては軽トラックの運転が必要となり、MT免許の取得が求められるケースもあります。
規模の大きい会社では、フォークリフトを運転する機会も多いです。
都会に住んでいて、週末に車を運転するくらいの人にとっては、日常的に機械を使うことに不安を覚えるかもしれません。
解消法1:就職後のフォロー体制を確認する
まずは面接等で応募先の企業に確認することが重要です。
- どのような機械を運転する可能性があるのか。
- 入社後に運転免許や資格を取得する機会があるのか。
- トラクター等の操作を他の社員が指導してくれるのか。
運転免許や資格が必要な場合、それを取得するために教習所や講習を受けられるのかも確認しましょう。
基本的には、入社後に会社負担で教習所などに通うことになりますが、場合によっては、入社前までに免許や資格を自費で取得するよう求められることもあるようです。
特に、普通自動車のMT免許は応募条件で「取得しておくこと」と明記されている求人が多いです。
また、免許や資格を持っていてもすぐに人並みに運転ができるとは限りません。
特に大規模経営の場合、目的に応じてトラクターの作業機を付け替え、整地や播種、畝立て、防除など、様々な作業を機械操作で行います。
未経験の社員に対して、どのように指導・フォローしているのか、会社の実情をしっかり確認しましょう。
解消法2:資格や免許を取得する
転職までに時間とお金に余裕がある場合、転職前から資格や免許を取得しておくのも一つの手です。
農業をする上で役に立つ資格・免許は以下の通りです。
- 大型特殊自動車免許
トラクターを公道で運転する時に必要になります。
特に大規模法人などで大型のトラクターを使っている場合、こちらの免許が必要になります。 - けん引免許
トラクターでけん引式の作業機を使う場合、けん引免許が必要になります。 - フォークリフト運転技能講習
意外に思うかもしれませんが、農業法人でフォークリフトを使う機会は結構多いです。
大容量の肥料(500kg袋)など、重たいものを運ぶ時などに活躍します。自社で選果場などを持っている場合、場内の荷物の移動や箱詰めした商品の積み込みなどでも使用します。
フォークリフトを運転するにはこの資格が必須です。 - 不整地運搬車運転者
あまり聞き覚えがないかもしれませんが、クローラー式(キャタピラ)の運搬車(キャリアダンプとも言います)を使う時には必須の資格です。
また、クローラータイプのフォークリフトを運転する時は、フォークリフトの資格に加えて、こちらの資格も必要になります。
ちなみに、フォークリフト運転技能講習と不整地運搬車運転者の資格については、先に大型特殊免許を持っていると、講習時間が短縮されますので効率的です。
不安6:キャリアプランが描けない

こちらも農業法人に限った話ではありませんが、転職した後のキャリアプランについて悩むことも多いと思います。
こちらについては私自身も現在進行形で色々と考えているところです。
解消法1:自分のキャリアについて考える
まずは自分がどのようなキャリアを構築したいのか考えることが重要です。
- 農業者として将来的には独立したい。
- ゆくゆくは転職先の会社で経営に携わりたい。
- 農作業の現場仕事をずっと続けていきたい。
- 農業の現場を知った上で、自分で農業支援する会社を設立したい。
などなど。
キャリアプランを考えてみて、そのキャリアを目指すために、転職先の会社でどのようなことに取り組むかを考えてみましょう。
ここで重要なのは、キャリアプランをガチガチに固め過ぎないことです。
『キャリアショック』という本で書かれていましたが、先行き不透明な昨今では、環境がすぐに変わります。ですので、大まかな方向性は意識しつつ、柔軟にプランを軌道修正していく姿勢が求められます。
『キャリアショック』については、次の記事も参照ください。
もう一つ重要なことは、キャリアを作るのは自分自身だということ。
会社任せにして「この会社は、自分にどんなキャリアプランを提供してくれるのだろう」という意識は捨てましょう。
「自分はこういうキャリアを築きたい。なので、この会社ではこういうことをしたい。じゃあこの会社ではこういうことをやらせてもらえるのだろうか」
という意識が重要です。
解消法2:面接などで確認する
自分のキャリアプランについて考えたら、それをもとに面接等で確認してみることも重要です。
例えば、将来的に独立就農を視野に入れているならば、そのような人向けの支援があるのかどうかを聞いてみましょう。その会社を辞めて独立した人の有無などを確認しても良いと思います。
ゆくゆくは経営などにも携わりたいと思っていても、その企業が「あくまで現場作業員が必要。現場のリーダーを目指してほしい」という考え方ならば、自分のキャリアプランとは合致しない可能性があります。
転職の面接は、双方の考え方やニーズをすり合わせる機会です。
自分のやりたいことがあるならば、それをきちんとぶつけてみましょう。
私も今の会社に転職する時、社長との面接で「将来的には経営にも携わりたい」という気持ちを伝え、その意向をふまえて採用してもらいました。
現在もその目標は持ちつつ、日々キャリアについて考えたり、農作業や農業経営などについて業務を通して学び続けています。
まとめ

これまで、未経験者が抱えがちな不安と、その解消方法について説明してきました。
個人的に一番大事だと思うのは、応募先企業との面接時にしっかりと確認することです。
転職の面接ではお互いの疑問点を解消することが重要ですので、臆することなくどんどん質問をしていきましょう。
さらに、全ての不安が転職前に解消できるわけではないということを理解するのも大切です。
身も蓋もないですが、「やってみないと分からない」ということもたくさんあります。
私も色々と準備して入社したつもりでしたが、実際に働いてみると、
- トラクターの運転が全然うまくできない
- それどころかMTの軽トラすら満足に運転できない
- 20㎏の農薬を1回運んだだけで息切れする
- 初めて播種作業をした日に、いきなり腰と股関節を痛める
などなど、苦労したことや失敗したことがたくさんあります。
(むしろ、今でも色んな失敗しています)
分からないことや失敗したことがあっても、しっかり自分から相談したり、ヘルプを伝えられれば、助けてくれる人は周りに必ずいるはずです。
悩み過ぎて行動できないのは勿体ないので、100%不安を解消できるとは思わず、ある程度のところまで解消できたら、あとは思い切ってやってみるという意識も重要です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
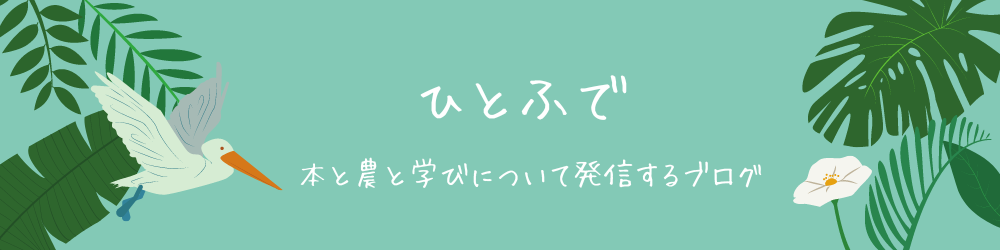









コメント