
こんにちは、秋富です。
このブログでは、農業法人等に就職して農業をする「サラリーマン就農」を推奨しています。
転職活動をする場合、ほぼ必ず企業の求人情報を参考にすると思います。
しかし、求人情報には様々な項目があり、全て読み込むのは結構面倒なことも……。
大事な部分を読み飛ばしたり、理解が不十分なままで応募してしまうと、入社後のミスマッチにつながってしまいます。
この記事では、求人情報を見る時に押さえておくべきポイントについて解説します。
求人情報をしっかり読み、自分の希望条件と照らし合わせ、理想的な転職活動につなげていきましょう。
求人情報の見方
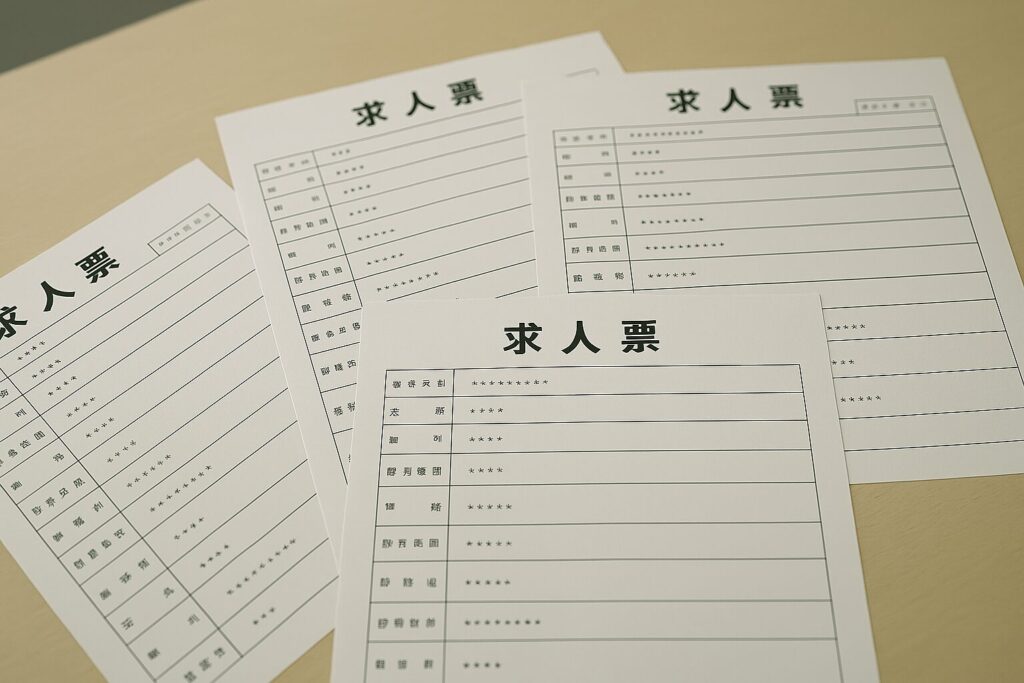
まずは求人情報の項目について説明します。
様々な項目がありますが、ここでは「職種」「雇用形態」「雇用期間」「就業場所」「通勤」「就業時間」「給与」「昇給」「賞与」「休日」「必要な経験、資格、免許」について、農業に関連する部分を中心に解説していきます。
それでは順番に見ていきましょう。
(1)職種
「職種」とは、従業員個人が担う仕事の種類のこと。
一般的な職種としては、営業職、研究職、事務職、企画職などがあります。
就職・転職活動でもまず注目する項目ですので、ご存じの方も多いと思います。
似た用語に「業種」がありますが、こちらは、企業が営む事業の内容のことです。
さて、農業法人の場合、職種がバリエーションに富んでいます。
例えば農業専門の求人サイト「あぐりナビ」では、「生産・飼育」「技能工/作業員」「営業/バイヤー」「事務」などの職種で検索できます。
これだけでは具体的な業務のイメージが付きにくいと思いますが、例えば農業現場の仕事をしたい場合は、「生産・飼育」や「技能工/作業員」で求人検索をしましょう。
そしてヒットした求人情報に書かれている「仕事内容」を見て、自分がやりたい仕事かどうかを確認していくと良いでしょう。
ハローワークの求人票では、「農業」や「農作業全般」など抽象的に書かれている場合もありますが、より具体的な業務内容を書いてくれている求人もあります。
例えば、「ぶどう栽培」「水田・畑作業員」「ミニトマト栽培スタッフ」「農作業機械オペレーター」などがあります。
具体的な業務内容については、「仕事の内容」という項目でしっかり確認するようにしましょう。
注意したいのは、農業法人でも複数の職種の募集があるということ。
例えば、事務職(経理や庶務)、営業職(作った生産物の販売等)での求人もよくあります。
自分がやりたい職種を整理し、それにマッチする求人を見るようにしましょう。
(2)雇用形態と雇用期間
雇用形態によって、その企業で働ける期間(雇用期間)が異なってきます。
まず「正社員」は、雇用期間の定めがない、つまり無期雇用としてその企業で継続的に働き続ける雇用形態になります。
正社員以外の雇用形態にも複数ありますが、ここでは「契約社員」と「パートタイム労働者」について説明します。
まず契約社員ですが、簡単に言うと雇用期間に限りのある社員ということです。
求人情報に、契約期間として「6か月」や「1年間」などの記載や、具体的に「2025年10月31日まで」のように日付が書かれています。
次にパートタイム労働者ですが、これはいわゆるパート、アルバイトとして働いている人のことです。
正社員や契約社員と比べて労働時間が短い雇用形態です。
厚生労働省の説明によると「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
パートタイム労働者の雇用期間については、有期(期間が決まっている)が多いものの、無期雇用の場合もあるようです。
また、有期雇用の契約社員やパートタイム労働者であっても、契約期間満了後に更新が行われ、継続して雇用してもらえる場合もあります。
「他の希望条件はマッチしているけど、雇用期間が決まっているのが気になる」という場合も、すぐには諦めず、契約更新の有無や正社員登用の可能性などをチェックすることが重要です。
求人情報の書き方があいまいな(「条件あり」などの表記)場合は、面接等で確認するようにしましょう。
さらに言えば、正社員を目指すことが必ず正解というわけでもありません。
私の会社では50人近くのパートさんがいますが、正社員ではなくあえてパートで働いている人もいます。
フルタイムで働かず、空いた時間で他のことに時間を使う、正社員になって重い責任を背負いたくない、など様々な理由があります。
個人の価値観なので正解はありませんし、ライフステージでも変わってくると思います。
今の自分の状況やこれから何をしたいのかを考えて、自分の雇用形態を見つけていくのが良いでしょう。
(3)就業場所と通勤
就業場所とは、実際に働く場所のことです。
特に農業法人の場合は、事業所の所在地と実際に農作業をする場所(=就業場所)が異なることがよくあります。
直接自家用車で就業場所に出勤する場合もあれば、一度事業所に出勤してから社用車などで就業場所に移動する場合もあります。
「自分が普段どこに出勤してどこで働くのか」をきちんと確認しておきましょう。
また、農業法人によっては事業所や就業場所に行くまでに公共交通機関がなく、車通勤が前提となる可能性もあります。
東京などの都心部から地方の農業法人に転職したい場合、就業場所までの通勤手段を確認しておくことも大事です。
個人的な印象ですが、地方だと大体マイカー通勤が前提のように感じます。
(4)就業時間
「就業時間」とは、業務開始から終了までの時間のことで、就業規則などで企業ごとに定められています。
「勤務時間」や「就労時間」と書かれている場合もありますが、同じ意味だと解釈して良いです。
ほとんどの求人情報で、「8:00~17:00」のように始業・就業時間が具体的に書かれています。
注意したいのは、就業時間には休憩時間も含まれているということ。
求人情報によっては、「休憩60分」などと明記されていたり、「実働8時間」のように休憩を差し引いた実際の労働時間を書いてくれていることがあります。
農業法人では、時期によって就業時間が変わることがあります。
(例)北海道で露地野菜を栽培している農業法人の場合
4~5月 8:00~17:00(休憩60分、実働8時間)
6~11月 5:30~16:00(休憩120分、実働8.5時間)
12~3月 9:00~15:00(休憩60分、実働5時間)
特に繁忙期の場合、深夜や早朝から仕事が始まる企業も珍しくありません。
また、後ほど詳しく説明しますが、農業法人には法律上、労働時間の規制がありません。
そのため、就業時間が「5:00~20:00」のような長時間に設定されている企業もあります。
「早起きが苦手」
「慣れない肉体労働で長時間働く自信がない」
といった不安を持つ人は、面接などで懸念している部分をはっきりと伝え、企業側に実態を聞いてみるのが大切です。
例えば、就労時間を長時間に設定していても、実際はそれより早く終わることがほとんどという企業もあります。
(5)給与
農業法人の従業員の平均収入については直近の統計データがないので正確には分かりませんが、求人情報を見ると、農業現場の仕事で概ね20万円~25万円が中心のようです。
「20万円~23万円」のように幅を持たせている企業もありますが、これは経験などによって給与の金額が変動するためです。
採用が決まった後、労働条件通知書や雇用契約書に実際の支給額が明記されます。
そのため、給与面での希望がある場合は、しっかり確認するようにしましょう。
面接などで企業側から条件面の説明があった場合、給与の話も質問しやすいかと思います。
企業側から詳しい説明がない場合は、「具体的な条件面についてはいつ頃教えていただけるでしょうか」のようにタイミングを尋ねる形で聞くと企業側も答えやすくなります。
遅くとも内定時には具体的な労働条件が示されるはずですので、そこで自分の納得できる金額かを確認しましょう。
(6)昇給と賞与
これらの項目については、制度の有無だけでなく前年実績をしっかり確認することが大事です。
昇給・賞与について「あり」と書いている企業であっても、「前年度実績なし」と書いている場合もあります。
例えば賞与について、制度としてはあるけれど、その年の売上によって支給の有無が決まるという企業もあります。
昇給についても、全員が定期的に昇給しているとは限りません。個人の成果によってそれぞれの昇給の有無が決まる場合や、数年ごとに全員が昇給するという場合もあります。
気になるのであれば、その企業における昇給や賞与の決まりと実績について確認をするようにしましょう。
(7)休日
休日も多くの人にとって気になる項目だと思います。
よく耳にする用語として、「完全週休2日制」と「週休2日制」があります。
「完全週休2日制」とは、毎週必ず休みが2日ある制度のこと。
一般的なのは土日が休みの場合ですが、別に土日でなくても、同じ週に休みが2日あれば完全週休2日制に該当します。
一方、「週休2日制」とは、年間を通して1か月に1回以上、1週間に休みが2日ある制度のこと。
例えば、1か月(≒4週間)のうち、1週目に休みが2日あって、残りの週は休みが各1日のみだった場合でも、週休2日制に該当します。
農業法人の場合、年間を通して完全週休2日制を導入している企業は少数派です。
繁閑差があること、天候に左右されること等から、特に繁忙期は休日が少ない印象です。
一方、閑散期については毎週土日が休みになる等、休日が増える場合もあります。
また、一般的な企業では、週1回以上の休日(もしくは4週で4日以上の休日)を与えることが法律で義務付けられていますが、農業の場合は適用除外となっています。
つまり、農業法人は休日を与えなくても法律上は問題ありません。
さすがに年間を通して全く休みがないというのは現実的ではありませんが、繁忙期の数か月間は休日がないという企業は聞いたことがあります。
その代わりに閑散期の数か月間はまるまる休日になるようです。
私の勤務先の場合、繁忙期は4週6休(4週間で6日休みを取る)、閑散期は完全週休2日となっています。
繁忙期は休みが少ないし就業時間も長いため、プライベートの時間はあまり取れませんが、閑散期にしっかり休んでいるのでバランスは取れていると感じています。
「どんな時も、絶対に毎週2日は絶対休みたい!」という希望がある人は、休日について応募先の企業にしっかり確認するようにしましょう。
(8)必要な経験、資格、免許
求人情報に、企業が求める経験、資格、免許等が明記されている場合もあります。
どんな経験や資格等を必要としているかは、企業によって異なります。
私のイメージですが、農業法人の求人情報でよく出てくるものとして、
- 農業に関する経験や知識
- 営業経験
- 普通自動車運転免許
- 大型特殊自動車運転免許
- フォークリフト運転技能講習
などがあると思います。
その経験や資格が「必須」なのか「あれば尚可」なのかは企業によって異なりますので、求人情報をよく確認することが必要です。
特に地方の場合、普通自動車免許はまず必須だと思います。
軽トラックの運転などのため、マニュアル免許が必要なこともありますので、確認を行いましょう。
また、大型特殊自動車運転免許やフォークリフト免許は農業法人で必要になる場面が多いため、すでに取得している場合は採用で有利になるでしょう。
なお、実際に働きだしてから、業務に関連する資格や免許を自主的に取得したいと思うようになることもあります。
そのような場合に企業側からの支援(受講料の負担、受講するための休暇取得など)があるのかどうか、確認してみるのもおススメです。
農業における労働基準法の適用除外

次に、農業法人が労働基準法の例外として扱われている労働時間や休日などの規制について説明します。
前職で一般企業に在籍していた場合、同じルールが農業法人でも適用されると考えていると、入社後のギャップにつながることもありますので、しっかり確認するようにしましょう。
(1)労働時間
労働時間とは、就業時間から休憩時間などを差し引いた時間のことです。
一般企業の場合、法律で「1日8時間、1週40時間以内」と定められていますが、農業法人の場合は適用されません。
極端に言えば、(4)就業時間でも説明したように一日何時間働かせても、法律上は問題ありません。
そのため、繁閑差の大きい企業の場合、繁忙期になると長時間労働が発生する可能性もあります。
(2)休憩
法律では、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなくてはいけない」とありますが、これも農業法人では適用除外となっています。
ただし、休憩しないと疲労が蓄積して作業能率が落ちますし、何より事故のリスクが増えます。
農業法人も、「安全配慮義務」は適用されますし、2025年6月からは熱中症対策も義務化されました。
このような理由から、休憩時間を与えない企業はほぼないと考えられます。
ただし、お昼休憩=必ず1時間与えられるというイメージがある方は、そうでない場合もありますので、求人情報などでしっかり確認をしましょう。
ちなみに私の勤務先の場合、お昼の1時間休憩以外に、10時と15時に15分ずつ休憩があります。
(3)休日
(7)休日でも少し触れましたが、農業法人では、休日の付与日数の規定についても適用除外となっています。
そのため、繁忙期の数か月間は休みがない企業というのも存在します。
とは言え、農業法人でも有給休暇の付与義務はあります。
例えば、週の所定労働時間が30時間以上の場合、6か月勤務すると初年度は10日、その後年々増加し、6年6か月以上で20日与えられます。
また、従業員から有給休暇の申請があった場合は企業側は原則拒否できません。
ですので「まったく休みが取れないのか」というとそんなことはありません。
ただし、「繁忙期なので有給が使いにくい」「他の人が休んでないのに自分だけ休めない」など、よくある悩みが農業法人でも起こり得ます。
面接などで休日の取得状況を確認するのが現実的かと思います。
(4)割増賃金
いわゆる休日手当、時間外手当、深夜手当と呼ばれるもののことです。
法律では、「1日8時間、週40時間を超える労働、法定休日と深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払わねばならない」とされています。
また割増率も法律で定められています。
農業の場合、深夜手当以外の割増賃金の支払い義務はありません。
(深夜手当とは、22時から翌朝5時までの間の労働に対して発生する手当です。)
注意したいのは、割増賃金は出なくとも、決められた時間(=所定労働時間)以上働いた場合、その分の賃金が発生する、ということです。
例えば、就業時間8:00~18:00、休憩1.5時間、所定労働時間8.5時間の農業法人があるとします。
この企業で20時まで残業した場合、実際の労働時間は10.5時間となり、所定労働時間を超えた2時間分の賃金は支払われる必要があります。
(ただし、その2時間分に割増率を上乗せする義務は企業側にはありません)
これまで農業法人における労働基準法の適用除外について説明してきました。
しかし、これらは「やらなくても違法ではない」ということであって、農業法人の中にはきちんと休日を付与したり、割増賃金を支払っている企業も存在します。
(あぐりナビやハローワークでも、そういった求人はたくさん見つかります。)
私の勤務先でも、時間外手当の支給や繁忙期の4週6休制度など、経営状況とにらめっこしながら、従業員にとって働きやすい仕組み作りに苦心しているようです。
不明点を解消する
ここまで求人情報の項目と、農業法人における適用除外について説明しました。
実際に求人情報を見ていくと、記載があいまいだったり、気になる部分について書かれていない場合もあります。
最後に、これらの不明点を解消していく方法についてお伝えします。
基本的には気になることがあれば企業側に確認することが最も手っ取り早く確実な方法だと思います。
企業と直接話す機会(面接など)を積極的に利用するようにしましょう。
まだ求人情報を見ているだけで、企業と直接コンタクトを取っていない場合、転職エージェントなどを通して確認するのがおススメです。
(1)転職エージェントの活用
別の記事で書いたように、農業求人サイトを使うと、無料で転職エージェントのサポートが受けられます。
私の場合「あぐりナビ」というサイトを使って転職しました。
この時、エージェントの方を通して、企業に色んな質問をしていきました。
直接聞きにくい年間休日や給与のことなども、エージェントの方がうまく聞いてくれて詳しく知ることができました。
また、ハローワークにしかない求人に応募したい場合、ハローワークを介して企業に問い合わせることができます。
(2)面接での質問
個人的には、面接は自己PRをする場でもありますが、それ以上にお互いのギャップを埋めるための機会だと認識しています。
そのため、面接の時に気になる点や不明点をどんどん聞いていくべきだと思います。
しかし、「お金のことや休みのことばかり聞くと印象が悪いのではないか」と思う気持ちもよく分かります。
その場合、質問の仕方やタイミングを工夫してみましょう。
例えば質問をする前に、「応募先企業に貢献したい」や「長期的なキャリアを築いていきたい」という企業にとってポジティブな気持ちをまず伝えると良いと思います。
まとめ
この記事では、求人情報のポイントと注意点について説明してきました。
全体を通して一番伝えたいことは、
- 自分の希望条件をしっかりと整理し、求人情報でその希望条件に合致する部分をしっかり確認する。
- 求人情報だけでは分からないことについては、エージェントなどを通して確認する。
- 面接でも企業側にきちんと確認する。
これらが大切だということです。
皆さんが自分の希望に合った理想的な転職をできることを願っています。
今回も記事をお読みいただきありがとうございました!
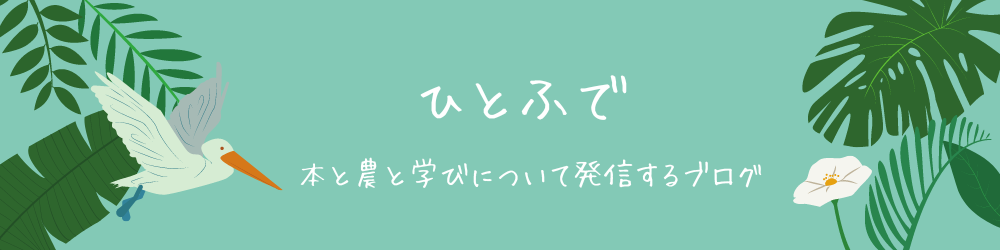


コメント